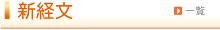兄は中学校の学制服を着て、弟は兄が去年まで着ていた、弟には大きめの上着を着ている。二人の息子は背がずいぶん伸びたが、母親は相変わらずその色あせた古いコートを着ていた。親切な声で「どうぞ、どうぞお入りください」と、おかみさんは挨拶すると、母親はびくびくしながら「すみません……、タンメンを一杯ください」言った。「かしこまりました、こちらへどうぞ」と、おかみさんは2番テーブルへ案内し、何事もなかったかのようにすばやく「予約席」と書かれたカードを隠した。それから、調理場にいる主人に向かって「タンメンを1つ!」と大きな声で注文を繰り返し、主人は「は〜い!タンメンを1つですね、少々お待ちください」と返事をすると同時に、3人分の麺を鍋に入れた。母と子三人はとても嬉しそうに話しながら食べている。台所にいる店の夫婦も彼らの嬉しそうな雰囲気に、心から喜んだ。そのうち、親子の会話からこんな話が聞こえてきた。「僕と淳君には秘密にしていたことがあって、ずっとお母さんには内緒にしていました。それは、淳君の書いた作文が北海道の代表に選ばれ、全国の作文大会で発表することになったことです。」……作文の内容は、「父が事故のため命を落とし、父の残した多額の債務返済の為、母は朝から晩まで必死で働いていることや、僕が毎日、朝と晩に新聞配達をしていることなど。」そして、一杯のタンメンが、本当に美味しかったですね。……三人でたった一杯のタンメンしか注文しなかったのに、お店のおじさんとおばさんは“ありがとうございます”“あけましておめでとうございます”と、挨拶してくれました!まるで僕たちに勇敢に力強く生きて、できるだけ早くお父さんの残した債務を返済するよう励ましてくれたかのようでした」「……淳君は大人になったら、タンメンの店を開こうと言いました。日本一のタンメンの店するのが夢です。しかも一人一人のお客さんに“ガンバレ、ご幸福を祈る、ありがとうございます”と励ましたいのです」。調理場で3人の会話を聞いていた二人の姿は突然消えていた。実は彼らは下にしゃがんで、一枚のタオルの端をそれぞれ掴んで、とめどなくあふれる涙を拭っていた……。
それから毎晩、北海亭では夜9時を過ぎると、2番テーブルには「予約席」と書かれたカードが置かれ、あの母と子三人を待っていた。しかし彼らは来ない。一年、二年、三年経っても、2番テーブルはやはり空いたままであった。結局それ以降、母と息子三人は姿を消し、二度と現れることはなかった。北海亭はますます繁盛し、店内は改装に伴いテーブルや椅子などを新しく入れ替えた。、ただあの2番テーブルは昔のまま、そこに置いてある。「どうしてあの2番テーブルだけが古いのですか?」不思議に思った客は尋ねると、おかみさんは一杯のタンメンの物語を皆に聞かせた。「……古いテーブルは店の真ん中に置かれ、自分達にとって、それは何か一種の励ましであるかのようで、またいつかその母と子三人が来たとき、このテーブルで彼らを歓迎するつもりです」。そのテーブルはいつの間にか「幸福のシンボル」となっていた。この話しは客から客へと広がっていった。さらに何年か経ち、ある年の大晦日、北海亭の商店街の店の主人達は閉店後、家族を連れて北海亭に集まり、食事しながら除夜の鐘を聞き、それから神社に参拝する。これは5,6年前からの習慣だ。
9時半を過ぎたころ、魚屋の夫婦が来ると、続々とその他の主人とその家族は食べ物とお酒などを持参して店に入ってきた。しばらくすると店の中は3、40人ほどになり、混雑したが、2番テーブルの事は誰もが知っているためか、今年の大晦日も2番テーブルは空いたまま、新年を迎えるのだろうと誰もが思った。
10時半過ぎ、店のドアが突然ゆっくりと開くと、店内は静まりかえり、皆の視線は入り口に注がれた。2人の青年が凛としたスーツ姿で、コートを手に持って店内に入った。二人を確認すると皆はようやく安心して、また店内は騒々しくなった。おかみさんは「申し訳ございません、すでに満席でございます」と断った直後、和服姿の婦人が2人の青年の間から現れた。店内の客はかたずを飲んで3人を見守った。婦人はゆっくりと、「あの…すみません…タンメンを3杯ください」。注文を聴いたおかみさんの脳裏には、十数年前の当時の若かったあの母親と二人の息子の記憶がよみがえり、十何年の歳月を経たあの三人と必死に重ねあわせた。調理場にいた主人も、あの3人を思い出し、「あ…あの…、貴方達は…」と指差しながら息が詰まってしまった。一人の青年はどうしたらいいのか分からない様子で、おかみさんを見て、ようやく話を切り出した。「私達母子三人は14年ほど前のある年の大晦日に、この店でたった一杯のタンメンをご馳走になって、そのタンメンに勇気付けられて、私達母子三人はようやく強靭に生きて行ける勇気を出せるようになりました。」……
この物語はここまでしか語れない。現在の現実的な価値観で判断すれば、店の夫婦二人はそれほど代価を払ってないが、たとえその位のタンメンであっても、心からの激励と祝福の意を込めた「ありがとう」や、「あけましておめでとう」などその程度の言葉であっても、悲惨な現実と窮地にに追い詰められた生命は、その言葉によって再び生きる勇気を見出すことが出来る。故にこのごく普通の行いであっても、生命の最も本質である善心からのものであれば、善の力がきわめて広く大きく作用するのである。
この物語は我々にある啓示をもたらした。我々自身はこの環境への影響力を無視するわけにはいかず、貴方達の善心による誠意ある配慮はこの世界の隅々に限りなき輝きと希望をもたらす事になるかもしれない。皆さん、人が助けを求めている時、支持を必要とする時に沈黙を守っていいのだろうか。皆さんの誰もが人類のこの家族の一員であり、これからは我々のこれまでの長く隠された善心を捧げるよう願い、それを明るく灯そう!たとえその善心は消えてしまいそうな明かりであったとしても、長い冬の寒い夜にとっては本当に光明かつ暖かい存在なのだ。