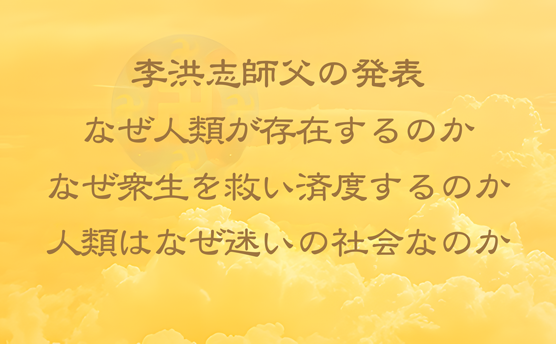漢字の中の先史文明(下)
リンクをコピーしました
Copyright © 1999-2025 Minghui.org.
世界には真・善・忍が必要です。
ご寄付により、さらに多くの人に真実の情報をお届けすることができます。明慧は皆さまのご支援に感謝いたします。
 明慧へのご支援
明慧へのご支援
関連文章